死の壁
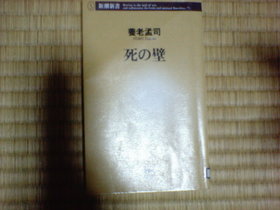 マンガ・ジャンキーな上に活字中毒者なのです。でも、マンガでも本でも一旦「いいな」と思った作者のものは、作品リストの端から端まで読んでみる、という読み方をします。だから偏ってるぞ~。
マンガ・ジャンキーな上に活字中毒者なのです。でも、マンガでも本でも一旦「いいな」と思った作者のものは、作品リストの端から端まで読んでみる、という読み方をします。だから偏ってるぞ~。
そういう「リストの端から端まで読んだ、リスペクトしている作者」の中に橋本治氏と養老孟司氏がいます。
このお二人に共通しているのは、「楽天性」と「体を動かせ」と「人も世の中も変わらないものは無い」でしょうか。1980年代からコアなファンがついていた方たちですが、橋本氏は「古典の現代語訳や辛口評論(ご本人はこれについては不本意らしいけど)」、養老氏は「専門の解剖学をベースにした、これまた辛口の文明論、社会論」という「いかにも売れなさそう~な」でもマニアにはたまらん本ばかり出しておられました。「ふっふっふ、だからこそあたしは読むのよ。」と、新刊が出るたびにチェックして本屋なり図書館なりに走り、舐めるように読み続けて21世紀となりました。なんちゅうの?ブレイク前のアイドルオタクみたいな心境?(いや、お二人ともちゃんと売れてたんだから、ちょっとこれは失礼だって。)
ところが、どういうわけか21世紀になってから、このお二人の著書がいきなりとんでもないバカ売れ大ヒットをして、たまげました。
橋本氏の「上司は思いつきでものを言う」と養老氏の「バカの壁」です。
嬉しかったけど、複雑。独り占めしてたのにって。
(いや、だから独り占めなんかしてないって)
それと同時に「ああ、世の中って変わっていくんだなあ。」としみじみ思いました。「偏屈な変わり者」であったはずの(なんちゅうご無礼をば。ほんとにファンか?)お二人の本が爆発的大ヒットする時代がくるとは。
「この世が永遠不変である。」と信じたがるのは「子供」でしょう。子供の頃は自分の周りの景色も人間関係も世の中も自分自身すらも変わる、ということが実感としてわかりません。大人になるにつれて、例えば身近な人間が亡くなる、景色が変わる、社会情勢も変わる、ことを実際に経験してしまいます。どんなに愛したものも、どんなに憎んだものも、時間がたてば心が変わっている自分に愕然としたり。
でも「この社会も自分も永遠不変である。」という前提以外を許さないのが高度成長期でした。「いつかは自分も死ぬ。いつかは社会も滅びる。」ことを見てみぬふりしてきた。そのツケが今まわってきているのです。(わたくし自身にもね)
バブルは崩壊したし、ベルリンの壁は崩れたし、阪神大震災は起こるし、地下鉄サリン事件、そして9・11事件。
「万物は流転する」のです。それをいたずらに不安がってどうする。怖い怖いという前にとりあえず体を動かせ。動かせば必ず脳も変わる。脳が変われば選択肢が増えて硬直した状況が動き出すぞ。状況が変われば楽天的になれる。終始一貫して養老氏の主張はこうです。
「楽天的じゃなきゃ、還暦を過ぎてから本がバカ売れしたりしないでしょ。」とは、Dr.ヨーローの名言。じゃっど。うわさでは新潮社では「『バカの壁』ヒット御礼ボーナス」がでたそうな。
「死の壁」(新潮新書)は「バカの壁」に続く第二弾。たくましいのう。かくありたきものよ。
私も好きです、このおふたり♪
養老さんに至っては、昆虫について語っている書まで購入してしまいました。私も好きになると全てを知りたくなってしまうんですよね~。偏る偏る(笑)。ナンシー関さんを語ったのも春さんとだったような気がします。
私もここ最近は死ぬまで生きるだけと思って過ごしています。死ぬまでに何をするか、誰と会うかだけ。全然人のことが気にならなくなってきました。比べることも全然なくなっちゃったし。そう思えると断然生きるのが楽です。
投稿: cluster | 2006年9月 5日 (火) 22時44分
おおう!clusterさんもファンでしたか!偏ってもしょうがないですよね(笑)。だって人生有限だし。
魚座は最近楽じゃありませんか?お互いしばらく前までシンドかったのが嘘みたですね。
投稿: 春 | 2006年9月 6日 (水) 09時01分