七草の考察
 全国でも「七草粥」行事が残っているところは珍しいらしいのですが、鹿児島は昔から「ななとこずし」と言って「7つになった子が隣近所の七軒を廻って七草粥をもらう」というしきたりがあります。
全国でも「七草粥」行事が残っているところは珍しいらしいのですが、鹿児島は昔から「ななとこずし」と言って「7つになった子が隣近所の七軒を廻って七草粥をもらう」というしきたりがあります。
今もやっているところがあるんじゃないでしょうか?
いろんなお宅のいろんな粥があって、七草全部じゃなくて五草ぐらいだったり、七草の替わりにホウレンソウとかハクサイとかが入っていたり、餅が入っていてどろどろしていたり、いろいろでした。7軒分もあればたいがいの量になり、7日どころか8日までかかって飽き飽きしました。正直お粥より、一緒にお年玉がもらえるのがうれしかったな。でもあれはうちの親もよその子に渡していたので、どこの親も平等に大変だったということかな。
全国に比べてなぜ鹿児島で七草が残ったか、考えてみたのですが。
つまりですね、今の暦は太陽暦で旧暦に比べて正月が約一月早いわけですよ。この時期他の地方では露地では七草が揃わないんじゃないでしょうか?鹿児島は温かいから今でもう全部生えているわけですよ。現にうちの庭でも「セリ・ナズナ・ゴギョウ・ハコベラ・ホトケノザ・スズナ・スズシロ」全部OKですもん。
他の地方じゃこうはいかないんじゃないかな?
吉野町では20代から70代の4人の女性農家が七草を栽培していて鹿児島市におろしているらしいです。縁起物だからみなさん本物を食べたいのでしょうね。しかしこれらはほとんど雑草に近い植物。かなり丈夫なはずです。なかなかいい商売であるといえます。


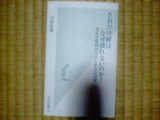










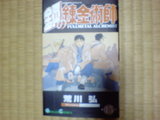

最近のコメント