のだめカンタービレ・15巻
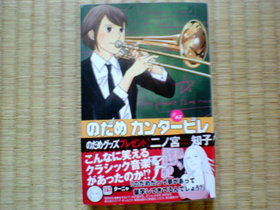 高校のときの担任のI先生は、謹厳実直を絵に描いたような英語の先生でした。
高校のときの担任のI先生は、謹厳実直を絵に描いたような英語の先生でした。
その人がかなりのモーツァルト・マニア。
モーツァルトの曲を1小節聴いただけでケッヘル№はすらすらでてくるし、英語の授業中もふとした拍子にモーツァルトを口ずさみ「いいよねえ♪いいよねえモーツァルト・・・」とつぶやいたり。
生意気盛りの高校生の頃、モーツァルトをいま一いま二も好きじゃありませんでした。ほら、十代ってなーんにも苦労した事ないくせに「人生とは・・・」「生きている意味って・・・」なーんて深刻ぶるのが好きなお年頃じゃないですか。モーツァルトみたいにどこに足がついているんだかわからない軽やかさは軽蔑の対象でした。いや、怖かったのかも。「こんないいかげんなやつに惚れたらダメ。惚れたらとことん振り回される。」やっとの思いでバランスをとってたあの頃。怖がってハリネズミのようになりながらちっぽけな自分を守ろうと必死。そんな人間にモーツァルトは鬼門でしょう。
あのクソまじめそうな先生の心のどこに、モーツァルトみたいな与太者の音楽が入る場所があったのか今となっては不思議に思います。あれから年月が流れて「モーツァルト・・・・・素敵♪」と素直に言えるようになった今、I先生と話がしたいなあと思う事があります。もうかなわぬ望みとなってしまいましたけれど。
というわけで「のだめカンタービレ・15巻」(二ノ宮知子著・講談社)です。
あいかわらずクラシックをとりまく奇人・変人・変態のオンパレードですが、15巻の極めつけは超絶モーツァルトマニアの元貴族、ブノワ氏が出色でしょう。のだめの初リサイタルを開いてくれるお城持ちの金持ちですが、筋金入りのモーツァルトマニア(んで、たぶん変態)。常日頃からモーツァルトかつらをかぶり、モーツァルト衣装を身に着け、コスプレに余念がない。新人の音楽家を発掘するのが趣味のありがたいパトロンだけど、弾かせるのは必ずモーツァルト・・・モ―ツァルト・・・。のだめの演奏指導には「ぱっかぱっか」とお馬の真似。
この強烈キャラにもまったく動じないのだめのキャラは本当に凄い。一緒になって「ぱっかぱっか」と二頭立てでお馬の真似。初リサイタルでモーツァルト以外聞く気のないブノワ氏にいきなりかますfffのリスト。「プランクトン多め」のラベル。
(のだめって変態で、その言動には大笑いさせられるけれど、いつだって誰にだってむちゃくちゃ真剣なんだよね。まじめなんだよ(かなりかたよっているけれど)。モーツァルトだってそう。スカトロマニアで変態でぶっ飛んでて、どうしようもないやつだったけれど、大まじめなんだよ。何に対しても。そこらあたりが大人になるとだんだんわかってきて、思うわけよ。あのクソまじめそうだったI先生は、実はとんでもなくおもしろい人だったかも知れないって。ガキだったからそこらあたりがわかってなかったんじゃないか?もったいないって。)
どうやらここらあたりから、のだめピアニストとしての生計がたってきそうな気配。のだめらしい普通のルート(チャイコフスキー・コンクールとかさ)からじゃないピアニストへの道を歩みそうだ。どうやって職業ピアニストになるんだ?ますます目が離せません!
初リサイタルお城編の最後で、ブノワ氏がちょこっとかつらを取ってみせる、こういうところの落とし加減も、あいかわらず絶好調!!



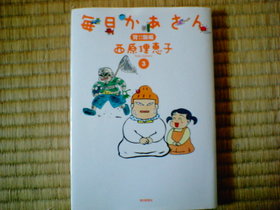





最近のコメント