嗤う伊右衛門
「どろどろどろどろ」静かにでもおどろおどろおしく鳴り響く和太鼓。
「ああ、幽霊がでてくる。幽霊がでてくる!!」
あれはよくできた効果音ですよね~。江戸時代に歌舞伎で使われていた効果音が、いまだに使われているわけです。怖いよ~~~。
「東海道四谷怪談」は傑作の多い歌舞伎の怪談話の中でもダントツの怖さだといいます。主人公のお岩様はとんでもない怨霊で、四谷怪談を舞台化したり映画化したり小説化したり、とにかくお岩様を表現するときには四谷のお岩稲荷にちゃんと詣でてからでないと、必ずや祟りがありましょう、ってんだからとんでもない。お岩様は著作権協会か?・・・・・・いやいや不遜な事は申しますまい。祟らないでね。パン!パン!(拝みました)。
「嗤う伊右衛門」(京極夏彦著・角川文庫)です。京極氏はこれを上梓するにあたって四谷稲荷に詣でたのでしょうか?
この作品は今まで伝えられてきたお岩様像とはまったく違う、美しく、素直で愛情深く、恨みのかけらもない誇り高い女性像として描いているのだけれど、・・・・・・でも、詣でたんだろうな。そういう作法をいかにも大事にしそうな京極氏。
「京極堂シリーズ」が大好きで、もちろん全部持ってるし、それどころか十回以上は読み返しているというぐらいのファンなんだけれど、「嗤う伊右衛門」を読んだのはずっと後でした。なにせ既存の「お岩様像」があまりにも強烈で。あまりにもどろどろベタベタじめじめして怖すぎなあの話を、どう料理しても「理不尽な不幸に、より理不尽な怒りで対抗する救いのない話」になるんだろうと思っていたので。
杞憂でした。これを読んでさらに「京極夏彦は凄い!!」と。
理不尽さはまるでなかったです。いや、不幸な理不尽はお岩様や伊右衛門殿に降りかかってくるんだけど(その元凶は伊東喜兵衛。こいつがまあどこをとっても救いようのない大悪党)、その理不尽に対して恨みを持ってこないの。なんというかクールなの。お岩様と伊右衛門殿が淡々と乾いた対応をして(伊右衛門が大工仕事が上手で寡黙な職人肌なのもポイント高し)、それがさらにより大きな理不尽の呼び水になるんだけれど、最後の最後まで二人は不幸ではない。それどころか「ああ、これはハッピーエンドなのだわ。」と思わされてしまう。普通には「ここまで陰惨な結末はないだろう」といえる狂気の沙汰な最後なのに。
読み終わった後に泣きましたね~。
「世界の蜷川幸雄」が小雪と唐沢寿明で映画化したので、これは見ねばならんと見ました。
わたくし的には「今まで見た邦画ベスト3」に入る感動作です。
主役の二人も美しかったですが、大悪党伊東喜兵衛を椎名桔平が怪演。衣装や調度の美術の趣味もよくて、伊東喜兵衛が持っていた人間が入りそうな大花瓶を欲しくなったほどでした。
歌舞伎の「四谷怪談」は今のシーズンの出し物。そう、この「嗤う伊右衛門」も今の時期にお薦めでございますよ。
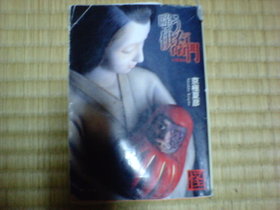
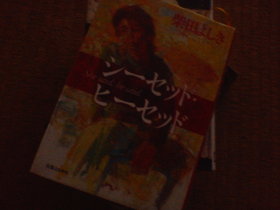
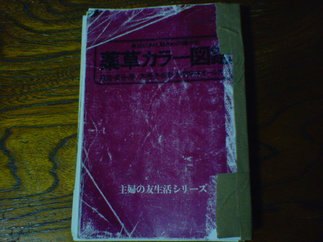







最近のコメント