西高東低の冬型
 夕方モモ(紀州犬雑種・女の子・4歳)がすごい勢いで家の中に飛び込んできて、「くうううん、くうううん、キャキャン!」と大騒ぎでした。また遠雷がなっているようです。
夕方モモ(紀州犬雑種・女の子・4歳)がすごい勢いで家の中に飛び込んできて、「くうううん、くうううん、キャキャン!」と大騒ぎでした。また遠雷がなっているようです。
天気図で見る限りでは、日本列島に縦に10本ぐらい等圧線が走っているようなモウレツな東の低気圧と、大陸に高気圧が鎮座してました。典型的な西高東低の冬型の天気です。実はうち近辺ではすごい勢いで雪が降っているのですが、残念なことにカメラに写りません。
「鹿児島市のチベット」とはいっても所詮は南国鹿児島のこと、1mも2mも一晩で積もってしまう雪国の苦労は想像もつきません。広島の中国地方の山のてっぺんに嫁に行った妹のところでは、もうかなりな雪が積もっているそうです。というより前回の雪が溶けてないのですと。ひゃあああ。そういうお話、いっそ怖いです。
小泉八雲の「雪女」は美しくも恐ろしく神話的なお話ですが、あのお話の舞台は決して雪国ではなく、関東地方だそうです。だから雪の夜は雪洞を掘って潜り込むのが(雪国のかまくらのように)一番暖かく、雪国の人間だったらそれをよく承知しているのに、「雪女」の炭焼き二人は、一番体温の下がりやすい小屋に泊まってしまったのだと。
知らぬということは恐ろしいことです。
なんにせよ、子供の頃白紫池(九州で唯一天然氷のはる霧島の池)にスケートに連れて行かれ、あまりの寒さにものの十分も滑らぬうちに泣いて帰った経験のある身としては、その後「スキー、スケート、スノーモービル」などという「雪」とか「氷」とかいう単語のつくものには金輪際近寄らぬようにしています。スキーを知らずとも人生オッケー!君子危うきに近寄らず。





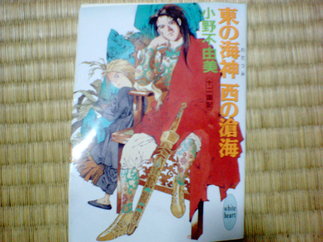




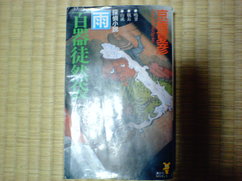
最近のコメント