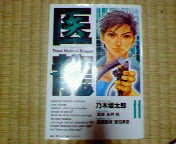 今の日本でこういう事を言うと、とんでもない偏屈と思われそうなんですが、TVをほとんど見ません。「TVなんてお下劣」などと考えているわけでは決してなく、どちらかというとだい好きだったはずなのですが・・・・・見なくなってしまったのです。
今の日本でこういう事を言うと、とんでもない偏屈と思われそうなんですが、TVをほとんど見ません。「TVなんてお下劣」などと考えているわけでは決してなく、どちらかというとだい好きだったはずなのですが・・・・・見なくなってしまったのです。
目が悪くて「見ていると疲れる」というのも大きな原因です。いったん見なくなりだすと、お話についていけなくなりますし。今は「TVを見るヒマがあったらその分マンガを読む」というのに徹底してます。よって「医龍がTV化された」というのは知ってますが、一度も見たことはありません。どのみちどんなに忠実な実写化でも結局は別物だもんな。わたくしにとってはマンガでもう充分お腹いっぱいなんででございますよ。
と、ここで「医龍・11巻」(乃木坂太郎著・小学館)です。
大盛り上がりに盛り上がった「バチスタ手術」が大成功に終わりました。朝田を天敵と嫌う木原の母親の心破裂縫合手術成功のおまけ付です。ここまでお膳立てが揃ったらこのまま「加藤、教授選有利、野口派一掃になだれ込む」方向に行くのか?と一瞬思いましたのに・・・・・
なんと由比正雪ヘアの鬼頭教授(わたくしの一番のお気に入り)、ほんとに第3の教授候補を連れてきちゃいましたよ!
その名も国立笙一郎、メリケン国はUCLAの教授様!!さすが鬼頭さま引っ張ってくる人材が一味も二味もちがいます!
いやあああ、ほー―ンと乃木坂氏、只者じゃありやせん。
この国立の出し方もむちゃくちゃカアッチョええ!11巻一番のお気に入りのシーンは、この国立と野口が教授室で初対決するシーンですな。「こんな男でも、年をとると、祖国の役に立ちたいと思うようになるものです。」だって。もう――かっちょええ!またこの国立のルックスが「いかにも年功序列の日本医学界に見切りをつけて、飛び出した先のアメリカで出世しそうな」濃いい、というかブラックっぽいルックスなんですわ。なんという画力じゃ。絵だけでこの説得力。
これで教授選の行方は全くわからなくなってきました。おもしろい!どう考えても今の状況下で加藤に勝ち目はないぞ?どうなるんだ?ますます目が離せない医龍なんでございました。
国立と野口の対決に同席した鬼頭教授が、野口の煙草の煙にもはや嫌悪感モロだしで、手でパタパタ煽いだりするところなんか、「もお――ん鬼頭教授ったら(はあと)」で萌え萌えでございました。








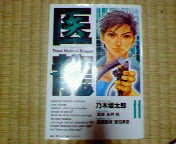

最近のコメント