手弁当のすさまじさ
それにしても、山羊サミットの準備委員会は10人あまりで構成されていたのですが、すごかったです。
何がどうすごいかというと、いわゆる手弁当のボランティアなのに、一年前から毎月一回づつ実行委員会が催される。そのたび、半月前に委員会の日がメールで通告され、行くとみなさんお仕事帰りなのに驚くべき出席率。
完璧なレジュメが用意されていて、一月の間に担当部署の仕事がどこまで段取りできたか、確認発表。ここで意見がつのられ、それぞれの担当部署との関わりと段取りを再検討。来月の実行委員会のだいたいの日取りを確認。これを一年間繰り返して少しづつ積み上げていって本番。
当日も、すごくて時間の流れ、場所、人員配置、すべてがちゃんと書面にしてあって配られできうる限り齟齬のないように、情報が統制されてました。鹿児島大学の先生が事務局を勤めておられたのですが、この手の催しでこれほど有能な事務局をはじめてみました。
また参加する実行委員会のメンバーみんなが、まじめで一生懸命なのです。「どこからこの情熱が?」と思わされるほどいまどき珍しい熱い現場でした。
「どこから?」
どうもみなさん、むちゃくちゃヤギが好きな方ばかりだったのです。
「好き」ってほんとにすごいなあ。
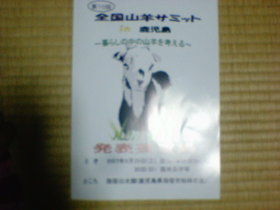









最近のコメント