ノブドウ
幼い頃からのマンガとTVの見過ぎで、ひどい近視と乱視です。コンタクトレンズも使っているので目が疲れやすく、必然的に「目にいい」と聞くと耳がそば立ちます。
ノブドウも昔から「突き目の薬」として民間で使われ続けてきた野草。それでなくてもこの実は赤、青、緑の間のあらゆる色調に熟すので、「秋に熟す実」のうち大好きBEST3に入ります。ちょっとした山の藪でも生えているので、見る機会があったらご覧になってください。虫食いや枯れが入った葉や蔓とあいまって、日本画そのもののような風情があります。
薬として使うのは茎から出る水。かなり水を吸い上げるらしく1,2時間でお弁当箱一杯ぐらいは溜まるとか。山仕事をする人たちは、それで目を洗ったり飲んだりしてきたのです。透明でちょっと渋くて少しだけ粘性のある水が目のゴミを洗い流してくれるのだそう。1度それをやってみたいなあと思いながら、実を楽しんでいるうちにいつも季節が変わってしまうのです。











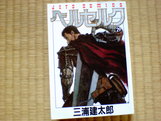
最近のコメント