 鳥インフルエンザに関するとても恐ろしい話を聞きました。
鳥インフルエンザに関するとても恐ろしい話を聞きました。
「全国ヤギサミット準備委員会」で元・鹿児島大学副学長で家畜の権威の萬田正治先生と同席することができお話を伺ったのです。
「『鳥インフルエンザの感染源が野鳥だ』というあれね、実はなんら確認されてないの。たまたま鳥取大のバカ教授がひとりだけ言ってたことを都合がよかったものだからそのままマスコミが使い続けてるだけだね。学会じゃ誰も言ってないよ。
―――――ホントなんですか?!
「だいたいなんで何万羽も飼っている『清潔で合理的な近代的養鶏場』だけがウィルスに狙い撃ちされてるわけよ?養鶏場そのものに原因があることは間違いないでしょうが。
―――――(確かにその通りだ。日本には平飼いで野生に近い状態で鶏を飼っている農家はごまんとある。そういうところで鶏の大量死が確認された報告はまだない。有機農法で合鴨を田んぼで放し飼いにしている農家も。まだぜんぜん無事だ。そういう連中のほうがはるかに野鳥に接する機会が多いはずなのに)
「日本が戦後やってきた畜産政策はものすごく危ないわけ。考えてもごらん今の大規模養鶏場の環境を。
- ほとんど同一の遺伝子を持つ大量の鶏のブロイラー養成。
- 多量の抗生物質を投入した輸入飼料(日本では人間に投与される抗生物質の総量の3~5倍が家畜に投与されている)
- 閉鎖され隔離され温度湿度まで人工的に管理された無菌室の環境(通常ならば悪玉菌を駆逐する善玉菌の存在も許さない)
この状況は何かに似ているだろう?
―――――生物化学実験室。細菌やウィルスの培養基。
「その通り!どんなに無菌に近い状態を作ったとしても、1立方mあたり1個や2個の細菌やウィルスは必ず存在する。そのウィルスにとって大規模養鶏場の鶏ほどおいしい餌はないだろう。こいつらに野生種のような抵抗力はまったくない。しかも同一遺伝子タンパクを持つ。加えて実に快適な環境。ウィルスにどうぞ繁殖してくださいといわんばかりだろう。
―――――そ、そんな、
「野生種は何千年もの間体内でウィルスを飼いならし弱毒性にしてきている。そういう意味ではとても安全だ。一番危険なのはこの実験動物に等しい養鶏場のブロイラーたちだよ。ウィルスは何万羽ものブロイラーの間を感染していく間に、進化し、強毒性となる。
なんという恐ろしいお話でありましょうか!!あまりのことに言葉を失いました。つまり鳥インフルエンザも病原性大腸菌O-157やノロウィルスと流行の原理は一緒なのです。人工的で(人間が考える)清潔な環境と、抵抗力のない個体が大量に集合している状況こそが流行の根本原因なのです。
―――――せ、政府はなぜ何も手を打たないのですか?
「利害が絡むからだよ。経済の原理だ。アメリカから義務化されている飼料穀物の輸入。抗生物質を販売する薬品会社。JA。ちょっと考えただけでも養鶏場形式の鶏飼育で利を得ている連中は山ほどいる。そして日本の農政は戦後何も考えていない。『ことなかれ』ばかり考えて結局失敗続きだ。これに関しては特にわたしも抗議しつづけているが、役人の頭というのはとにかく固い。
あまりにも恐ろしいお話だったのでいてもたってもいられず、ブログに載せました。あとはこの文章を読んだみなさまのご判断にお任せいたします。



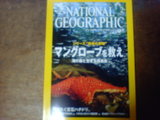






最近のコメント